谷川岳・西黒尾根 2019.6.18 レポート
2019年6月18日(火)
岩稜実践「西黒尾根から登る谷川岳」

朝4時
土合口を出発
ロングルートを1日で歩くため
山麓に前泊しました

西黒尾根は日本三大急登のひとつ
タフな登りが
ここから始まります

登り始めて約20分
鉄塔がある眺望ポイントで日の出

夏至は4日後
昼の長さを味方につけたチャレンジです

昨日まで悪天、明日からも悪天
今日がアタック日で本当にラッキーです

この時期の谷川岳は
残雪とお花が楽しめます

標高が上がるにつれ
美しいお花がお出迎え

イワカガミ

ウスユキソウ

他にもたくさんの高山植物が
岩と格闘する私たちを
足元で励ましてくれています

そう、西黒尾根は
岩場鎖場が連続するルートなのです

でも、今回は岩場の練習を積んでいるメンバーばかり
落ち着いて登っていけば
問題ありません

アルプス並の絶景もこのコースの魅力
景色、花、岩と
飽きることがありません

あんなに遠かったザンゲ岩が
もう目の前
ここまでくれば
あともう少し

肩の小屋直下には
やはり残雪がありました
空気もいきなりひんやり

肩の小屋に荷物をデポし
谷川岳山頂へは手ぶらでアタック

今日登ってきた西黒尾根の全貌が見えました
一歩一歩を積み重ねて
今ここに立っているのだと思うと
あらためて感動してしまう
今回参加してメンバーのほとんどが
この夏、槍ヶ岳や穂高の岩稜登山を予定しています
三大急登を登りきっただけでなく
疲れずに登れたことが
大きな自信につながりました
本番まであと数カ月
体のケアをしながら
実践力をつけていきましょう!
Copyright © TRACE All Rights Reserved.
岩稜実践「西黒尾根から登る谷川岳」
朝4時
土合口を出発
ロングルートを1日で歩くため
山麓に前泊しました
西黒尾根は日本三大急登のひとつ
タフな登りが
ここから始まります
登り始めて約20分
鉄塔がある眺望ポイントで日の出
夏至は4日後
昼の長さを味方につけたチャレンジです
昨日まで悪天、明日からも悪天
今日がアタック日で本当にラッキーです
この時期の谷川岳は
残雪とお花が楽しめます
標高が上がるにつれ
美しいお花がお出迎え
イワカガミ
ウスユキソウ
他にもたくさんの高山植物が
岩と格闘する私たちを
足元で励ましてくれています
そう、西黒尾根は
岩場鎖場が連続するルートなのです
でも、今回は岩場の練習を積んでいるメンバーばかり
落ち着いて登っていけば
問題ありません
アルプス並の絶景もこのコースの魅力
景色、花、岩と
飽きることがありません
あんなに遠かったザンゲ岩が
もう目の前
ここまでくれば
あともう少し
肩の小屋直下には
やはり残雪がありました
空気もいきなりひんやり
肩の小屋に荷物をデポし
谷川岳山頂へは手ぶらでアタック
今日登ってきた西黒尾根の全貌が見えました
一歩一歩を積み重ねて
今ここに立っているのだと思うと
あらためて感動してしまう
今回参加してメンバーのほとんどが
この夏、槍ヶ岳や穂高の岩稜登山を予定しています
三大急登を登りきっただけでなく
疲れずに登れたことが
大きな自信につながりました
本番まであと数カ月
体のケアをしながら
実践力をつけていきましょう!
Copyright © TRACE All Rights Reserved.
ウォーターハイキング「西丹沢大滝沢中流」2019.6.16 レポート
2019年6月16日(日)
ウォーターハイキング「西丹沢大滝沢中流」

じゃーん
いつもとぜんぜん違ういでたち

そう、今日はウォーターハイキング!
太陽が顔を出し
暑くなりそうです

水に浸かる瞬間は
いつもドキドキ

足首ほどだった水位が
太ももの深さに

そして
次々と現れる滝

真下にくると
しぶきがスゴイ

ここはとても越えられない
という場所は
高巻きます

越えたら
また沢の中へ

木漏れ日に輝く沢は
言葉にできないほど美しい

一方、水流と岩のぬめりで
よろけることしばしば

顔に水しぶきを受けながら
激流にも挑戦

最後に現れた50mの「地獄棚」
水の流れ、光の入り方
フィナーレを飾るにふさわしい滝です
ここまで登ってきてよかった
「見る」と「やる」はこんなにも違う
と思わせてくれるウォーターハイキング
ぜひ一度ご体験を!
Copyright © TRACE All Rights Reserved.
ウォーターハイキング「西丹沢大滝沢中流」
じゃーん
いつもとぜんぜん違ういでたち
そう、今日はウォーターハイキング!
太陽が顔を出し
暑くなりそうです
水に浸かる瞬間は
いつもドキドキ
足首ほどだった水位が
太ももの深さに
そして
次々と現れる滝
真下にくると
しぶきがスゴイ
ここはとても越えられない
という場所は
高巻きます
越えたら
また沢の中へ
木漏れ日に輝く沢は
言葉にできないほど美しい
一方、水流と岩のぬめりで
よろけることしばしば
顔に水しぶきを受けながら
激流にも挑戦
最後に現れた50mの「地獄棚」
水の流れ、光の入り方
フィナーレを飾るにふさわしい滝です
ここまで登ってきてよかった
「見る」と「やる」はこんなにも違う
と思わせてくれるウォーターハイキング
ぜひ一度ご体験を!
Copyright © TRACE All Rights Reserved.
はじめてのヒマラヤ登山2019 報告レポート③
はじめてのヒマラヤ登山2019
「アンナプルナサンクチュアリからヒマラヤのピークへ!」
2019年4月21日(日)〜5月6日(月)
CONTENTS-------------
Part①「旅立ち」
Part②「ネパール上陸」
■Part③「荷物が来ないけどキャラバン始まっちゃった」(2019.4.23)

朝5時
ホテルのロビーにメンバーが集合

キャラバンの荷物は
すべてこのダッフルバッグに詰め込みました

2人の荷物はまだ届いていません
でも、待っていると登頂ができなくなってしまうので
ひとまず先へ進むことに
現地エージェントにお借りしたシューズで
取り急ぎ出発です

私たちの専用バス
照明が微妙ですが
この車が登山口まで運んでくれます

明るくなった車内はこんな感じ
年季十分
シートベルトもあってないようなもの

小さいことは気にしない〜♪
なんたって、ネパールの旅が始まったのですから
カトマンズの街を抜けて
一路ポカラへ

朝食はをホテルのお弁当
サンドイッチにチョコマフィン
ゆで卵2個、バナナとリンゴ
そしてジュース

途中、コーヒースタンドにも寄ってくれました
のんびり旅です

ポカラに着いたのはちょうどお昼
このお店でランチします

ネパールの国民食ダルバート
ご飯とダルスープはおかわり自由
お腹いっぱいいただきました
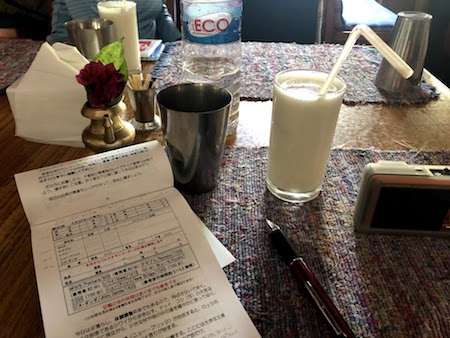
ここでしばらく待機
ロストバゲージに関する連絡が
カトマンズから入ることになっています

結局、2人の荷物は
経由地のクアラルンプールで見つかりました
明日以降、輸送が始まるので、
私たちの手元に届くのは2〜3日後とのこと
となれば、当面必要なものをポカラで買い揃えなければなりません
さっそく、お買い物です

ポカラでトレッキング装備を調達すると
ほっとひと安心
その後、バスは悪路で大揺れだったのですが
全員、深い眠りに落ちました

ポカラから2時間半
気づけば陸路の終点「シワイ」に着いていました
ここからトレッキングが始まります

時刻はすでに18時
行けても、一番近い村「キューミ」までになりそうです
それでも、進みます! いや進みたい!
待ちに待ったキャラバンスタートです!
>>Part4へ続く
Copyright © TRACE All Rights Reserved.
「アンナプルナサンクチュアリからヒマラヤのピークへ!」
2019年4月21日(日)〜5月6日(月)
CONTENTS-------------
Part①「旅立ち」
Part②「ネパール上陸」
■Part③「荷物が来ないけどキャラバン始まっちゃった」(2019.4.23)
朝5時
ホテルのロビーにメンバーが集合
キャラバンの荷物は
すべてこのダッフルバッグに詰め込みました
2人の荷物はまだ届いていません
でも、待っていると登頂ができなくなってしまうので
ひとまず先へ進むことに
現地エージェントにお借りしたシューズで
取り急ぎ出発です
私たちの専用バス
照明が微妙ですが
この車が登山口まで運んでくれます
明るくなった車内はこんな感じ
年季十分
シートベルトもあってないようなもの
小さいことは気にしない〜♪
なんたって、ネパールの旅が始まったのですから
カトマンズの街を抜けて
一路ポカラへ
朝食はをホテルのお弁当
サンドイッチにチョコマフィン
ゆで卵2個、バナナとリンゴ
そしてジュース
途中、コーヒースタンドにも寄ってくれました
のんびり旅です
ポカラに着いたのはちょうどお昼
このお店でランチします
ネパールの国民食ダルバート
ご飯とダルスープはおかわり自由
お腹いっぱいいただきました
ここでしばらく待機
ロストバゲージに関する連絡が
カトマンズから入ることになっています
結局、2人の荷物は
経由地のクアラルンプールで見つかりました
明日以降、輸送が始まるので、
私たちの手元に届くのは2〜3日後とのこと
となれば、当面必要なものをポカラで買い揃えなければなりません
さっそく、お買い物です
ポカラでトレッキング装備を調達すると
ほっとひと安心
その後、バスは悪路で大揺れだったのですが
全員、深い眠りに落ちました
ポカラから2時間半
気づけば陸路の終点「シワイ」に着いていました
ここからトレッキングが始まります
時刻はすでに18時
行けても、一番近い村「キューミ」までになりそうです
それでも、進みます! いや進みたい!
待ちに待ったキャラバンスタートです!
>>Part4へ続く
Copyright © TRACE All Rights Reserved.
6月の山ジムLight 2019.6.9 レポート
2019年6月9日(日)
山ジムLight「万六尾根から生藤山」

この季節
樹間を抜ける風が気持ちいい奥多摩の「万六尾根」

しかし、2日前に梅雨入りした関東地方
その直後からしっかり雨が降っています

雨具を着て登ると歩きづらい
これも負荷の1つなんです

でも、気温が低めなのは
むしろトレーニングには好都合
今日は少し心拍を上げて歩いてみます

本日の最高ピークは
ここ生藤山

心肺と筋力が「ややきつい」くらいを目安に
気持ちよく登ってきました

心拍数をコントロールして
うまく歩けたでしょうか

下山途中の「軍刀利神社奥の院」
御神木の存在感に圧倒されました

ここは水の神様でもあるそうです
なるほど
雨で潤う森がいつも以上に美しく見えたのはそのせいなのかも
私たちは、すっかり濡れてしまったけど
6月らしい登山が楽しめた気がします
【トレーニングDATA】
コース:武蔵五日市駅(9:00発 数馬行き バス乗車30分)柏木野バス停ー連行山ー生藤山ー軍刀利神社ー井戸バス停
性別:女性
有酸素ゾーン(目標心拍ゾーン):112-147
最大心拍数:161
平均心拍数:117
トレーニング時間:5時間00分58秒
time in zone(ゾーン内): 4時間38分52秒
above(ゾーン以上):23分35秒
below(ゾーン以下):1時間08分46秒
消費エネルギー:1,593kcal
*数字は休憩時間を含むCopyright © TRACE All Rights Reserved.
山ジムLight「万六尾根から生藤山」
この季節
樹間を抜ける風が気持ちいい奥多摩の「万六尾根」
しかし、2日前に梅雨入りした関東地方
その直後からしっかり雨が降っています
雨具を着て登ると歩きづらい
これも負荷の1つなんです
でも、気温が低めなのは
むしろトレーニングには好都合
今日は少し心拍を上げて歩いてみます
本日の最高ピークは
ここ生藤山
心肺と筋力が「ややきつい」くらいを目安に
気持ちよく登ってきました
心拍数をコントロールして
うまく歩けたでしょうか
下山途中の「軍刀利神社奥の院」
御神木の存在感に圧倒されました
ここは水の神様でもあるそうです
なるほど
雨で潤う森がいつも以上に美しく見えたのはそのせいなのかも
私たちは、すっかり濡れてしまったけど
6月らしい登山が楽しめた気がします
【トレーニングDATA】
コース:武蔵五日市駅(9:00発 数馬行き バス乗車30分)柏木野バス停ー連行山ー生藤山ー軍刀利神社ー井戸バス停
性別:女性
有酸素ゾーン(目標心拍ゾーン):112-147
最大心拍数:161
平均心拍数:117
トレーニング時間:5時間00分58秒
time in zone(ゾーン内): 4時間38分52秒
above(ゾーン以上):23分35秒
below(ゾーン以下):1時間08分46秒
消費エネルギー:1,593kcal
*数字は休憩時間を含むCopyright © TRACE All Rights Reserved.
岩登り「鷹取山」2019.5.30 レポート
2019年5月30日(木)
岩登り「鷹取山」
夏山に向けての岩場練習として
湘南「鷹取山」に来ました

まず最初に
岩場を安全に登り下りするためのポイントを学びます
体の使い方、バランスのとりかたなど
いくつかのコツを頭に入れたら

その後は実践です
いつも履いている登山靴でOK
小さな足場でもうまく体重をのせることができれば
安定して登っていけます

感覚がつかめてきたら
てっぺん目指して登ってみましょう
最初はダメだと思った難関も
手の位置、足の位置、体重移動を駆使すると
突破していけるものです
実際の山より
やや難しい練習をしておくことと
本番で落ち着いた行動ができるようになります
もちろん、岩と格闘しながら無我夢中で登っていく楽しさもあります
登山の技術アップに、ぜひ取り入れてみてください
Copyright © TRACE All Rights Reserved.
岩登り「鷹取山」
夏山に向けての岩場練習として
湘南「鷹取山」に来ました
まず最初に
岩場を安全に登り下りするためのポイントを学びます
体の使い方、バランスのとりかたなど
いくつかのコツを頭に入れたら
その後は実践です
いつも履いている登山靴でOK
小さな足場でもうまく体重をのせることができれば
安定して登っていけます
感覚がつかめてきたら
てっぺん目指して登ってみましょう
最初はダメだと思った難関も
手の位置、足の位置、体重移動を駆使すると
突破していけるものです
実際の山より
やや難しい練習をしておくことと
本番で落ち着いた行動ができるようになります
もちろん、岩と格闘しながら無我夢中で登っていく楽しさもあります
登山の技術アップに、ぜひ取り入れてみてください
Copyright © TRACE All Rights Reserved.